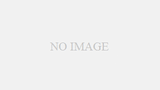2019年の業務の振り返りです。備忘がメインではありますが、ご依頼を検討されている方や中小企業診断士として活動したいと思っている方の参考になれば幸いです。
開業
4月に開業届を出して中小企業診断士事務所を開きました。事務所といっても1人事務所なのでフリーランスみたいなものですが。
1人でも事務所を名乗れるのはある意味士業保有者のメリットといえるかもしれません。
2017年に知人の弁護士と立ち上げた法律事務所での業務も引き続き行っているので、独立診断士と企業内診断士の中間のようなものです。
↓以前の記事も参考にどうぞ。
開業届
個人事業主なので定款等もなく、電子申請で終わりです。併せて青色申告の申請も行いました。
青色申告特別控除の65万円は大きいので、開業の際は青色申告の申請を併せて出すことをおすすめします。
デメリットとしては貸借対照表を作成する手間が主に挙げられますが、控除があろうとなかろうと複式簿記は経営分析に欠かせませんので経営者なら行っておくべきです。
ホームページ作成
このページですね。元々法律事務所のホームページを作ったりもしているので作成自体は大して時間もかかりませんでした。
ただ、作ったのは良いものの、更新しないと意味がありません。9月くらいまでは何とか記事更新もしていましたがその後滞ってしまったのでここは反省点です。そのせいでホームページからの問い合わせはスパムメールしか来ませんでしたし、今年は情報発信も心掛けたいと思います。
主な依頼ルート
知人
残念ながら世の中に「誰でも良いから中小企業診断士を探している」という人は稀です。となると自分自身の力量を知ってもらわないことには仕事は来ません。
というわけで、まずは自分の力量を知ってくださっている知人からの紹介が主でした。
特に前職で一緒に仕事をさせていただいていた方には私の仕事ぶりも良く知ってもらえているので、真っ先に仕事を依頼していただけました。
独立するにしても「辞め方」は大事
企業に勤めつつ診断士の資格を取って、独立すべきか否か考えている方もいるかと思いますが、何にしても勤めている内はそこでの業務に打ち込んだ方が良いです。
「どうせ辞めるし」と思って適当に仕事をする人には仕事をお願いしようと思いませんし、そんな仕事の仕方ではスキルも身に付かず無駄な時間を過ごすだけです。
前職の退職から3年近く経ちますが、当時の同僚や上司と会う機会は未だに多々ありますし、当時学んだ知識やスキルは今も役立っています。
職場環境も様々でしょうし一概には言えませんが、極力実のある過ごし方をしてから独立したいものです。
ポータルサイト
試しに色々登録してみたせいで若干収拾がつかなくなりましたが、主に使っていて仕事につながっているのは2つくらいですかね。
弁護士などは弁護士法の規制により紹介手数料方式が取れないためポータルサイトは月額制が主になりますが、診断士は幸か不幸か独占業務が無い代わりに業務規制も無きに等しいので、無料登録のポータルサイトが使えるのはメリットといえばメリットかもしれません。(手数料は引かれますが)
ビザスク

ほぼ経営相談に絞られるので、診断士が使うにはちょうど良いと思います。業種・業界特化の相談が多いので特定の業界に強い方だと尚良いかと。
公募案件に応募するパターンもあれば、ビザスク社のエージェント経由で直接ご依頼をいただくこともあります。(いつもありがとうございます)
そういえばこのサイトを教えてくれたのも前職の先輩なので、改めて人との繋がりは大切にするものだなぁと。
ランサーズ

たまに無性にexcel作業がしたくなるのでそういった案件に繋がればと思って登録しましたが、思いのほか幅広い種類の依頼があります。
幅広すぎてお断りすることも多々あるのがデメリットではあります。
登録されている方の属性も様々ですが、「中小企業診断士」と書ける点は差別化や信頼性に繋がるので診断士の資格メリットは多少活かせるように思います。
ポータルサイトも情報開示が重要
ホームページと同様ですが、ポータルサイトも登録すれば即依頼に繋がるというものでもありません。
どういう経験をしていて、どういうスキルがあって、どのような悩みを解決出来るのかわからないと依頼しようと思ってもらえません。
言っておいて私もまだまだなので、掲載内容の充実も引き続きやっていかねばなと考えております。
営業に来られた方
営業電話やメールを全て無視する方も多いですが私は割と聞く方です。
生の声を聞くことで当該業界の勉強にもなりますし、自分では必要なくとも顧問先で必要なサービスであることもあるので、引き出しを増やす意味でも極力時間を取って話を聞くようにしています。
その際、販促方法その他の提案をこちらから行い、逆にこちらに経営改善の支援を依頼してもらうケースもそこそこあります。
こちらとしても相手の商材を理解した上で支援に移れるので進めやすいですしWIN-WINな気がします。
かといって悪徳セールスに掴まるリスクもあるので絶対に聞くべきとまでは言えませんが・・・。
主な案件
通信業界の相談
思いっきり前職(NTT)のふんどしで相撲を取っていますが、使えるふんどしをわざわざ封印する必要も無いので使っています笑 守秘義務は勿論守りますが。
通信業で起業しようとしている方からの相談もあれば、通信業からの依頼を受けたコンサルタントの方からの相談もあります。
固定通信業にしても移動通信業にしても相互接続や光コラボレーションモデルなど、ビジネスモデルが若干わかりづらいのでその解説や市場動向の説明を行うことが多いです。もっぱらスポットでの相談ですね。
ビジネスモデルについては今年、何かしら記事にして公開したいと思います。
資金調達の相談
本業は事業計画作成なので、ある意味本業です。本来は融資を受けようと受けまいと計画は作ってほしいところですが、そこは引き続き啓蒙していく課題として、現状は「お金を借りたいので計画を作ってほしい」という依頼がメインです。
ただ、私の拘りとして「借金のための計画」は作りません。
計画はまず「経営を改善するためのもの」であり、調達可能性を高めるためだけの見せかけが綺麗な計画は意味がない、むしろ長期的には逆効果であると考えております。
なので、経営全般にどんどん踏み込みます。過去決算も各勘定科目の計上内容は事細かに確認しますしビジネスモデルの改革や新規施策の提案も行います。
事業計画作成を専門家に依頼する意味
ある意味では依頼した方が依頼者自身の稼働も増えるかもしれませんが、事業計画作成を専門家に依頼するメリットは時短効果や調達可能性の増ではありません。
資金を調達することがゴールではなく、調達した資金を活かしてより良い経営を実現することが必要であり、そのためには現状どのようなリソース・強みがあり、それをどう活かしていくか、調達した資金で取り組みをどのように加速させていくか整理する必要があります。
専門家と協力して計画を作る過程において自社の経営状況の深い理解やビジネスモデルの改善が行えることが依頼のメリットとなるよう活動しています。
経営革新等支援機関
12月に認定されました。単なる肩書に過ぎないではありますが、融資の力添えになれればと思います。
中小企業診断士であれば認定のハードルは低いので、これも資格取得のメリットかもしれません。(無資格での認定ハードルはわかりかねますが)
中小企業診断士業務
資格名称から想像されるような、俗にいう「診断業務」はやっておらず、あまり診断士的な動きはしていないのですが、東京都の「プロモーション支援事業」の支援専門家としては活動しました。
「プロモーション」というほど大層なものでもなく、提供しているサービスの強みを整理するに過ぎないのですが、やってみて思うのは「強みを強みとして認識していない」ケースが多いことです。
過去に解約されたことが無いとか、ユーザから直筆のお礼の手紙が届くとか、本人にとっては普通のことでもそれは十分に強みです。
相談料は公社から支払われるため依頼者負担はありませんので、自社サービスにどうも自信が持てない方は活用されると良いのではないでしょうか。2020/2/14までは受け付けているようです。(予算が無くなるまで)
その他
その他には経理関係の相談(仕訳の入れ方や経理担当者の研修など)や経営者自身のキャリア相談なんかが多いですかね。
特に経理周りは担当者1名のみの企業も多く、退職で有スキル者がゼロになってしまったという話も多く聞くので、自働化含めて提案の引き出しを増やしていきたいところです。
総括
後半~年末にかけて継続的なご依頼もいただくようになってきましたが、再現性のある営業ルートが確立出来たとはいいがたいので2020年はより情報発信を行うよう心掛けたいです。
また、コンサルは依頼企業の業績が改善しないと存在価値が無いと思いますので、2019年に依頼いただいた案件については引き続き確りと支援出来るよう励む所存です。
本年もよろしくお願いいたします。